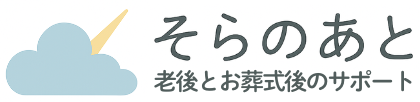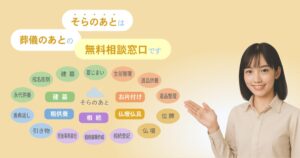葬儀が思っていたより高かった?!
はじめに
葬儀が終わった後のお客様から出てくる言葉に多いのが、『思っていたより葬儀代が高かった・・・』『小さな葬儀を依頼したけど、小さくなかった・・・』です。それもそのはず、葬儀代には階層があって、見えにくい(予想しづらい)料金が多いのですから。
さて、私はお葬式後のトータルサポート「そらのあと」の事業を始めるまで15年以上、葬儀社に勤めていましたので、一般の人よりも葬儀業界や各葬儀社の傾向を知っているつもりです。例えば、顧客第一主義でホスピタリティを重んじる誠実な葬儀社もあれば、広告では料金を低く見せて追加料金が多い会社や人材不足でサービスレベルが残念な会社など。葬儀社に属していた当時は、業界や同業他社の批判になりかねないため、それを大っぴらにすることはできませんでしたが、今はそうではありませんので、中立的な立場で情報開示できるようになりました。ちなみに、私が勤めていた葬儀社は「顧客第一主義でホスピタリティを重んじる誠実な葬儀社」でした。
わかりづらい広告表記
葬儀代が思っていたより高くなる要因は大きく分けて2つです。それは、「わかりづらい(誤解を与えやすい)広告表記の仕方」と「見えない追加料金の存在」です。それでは、「わかりづらい(誤解を与えやすい)広告表記の仕方」から触れてみたいと思います。
みなさん、「家族葬」という言葉は聞き慣れていることでしょう。そして、家族葬は「家族だけの小規模なお葬式」という認識の人は多いと思います。しかし、家族葬の定義は、一部の葬儀社の広告により、ここ数年で変わってきています。
さて、「直葬(ちょくそう)」という言葉はご存じでしょうか。その話をする前に、葬儀というのは、「通夜式・告別式(葬儀式)・火葬」の三部構成になっています。通夜式と告別式は、家族や親戚などの関係者により執り行う儀式で、火葬は火葬場で故人を荼毘に伏し(=焼くこと)、収骨(=骨上げ)する行為のことで、儀式ではありません。その通夜式と告別式の儀式を省き、火葬のみで済ませる方法を「直葬」と呼びます。
このように、直葬は儀式をおこなわないため、最もお金のかからない方法といえ、税別で76,000円~150,000円が相場です。ところが、前述の通り直葬は儀式ではありませんので、火葬の予約時間にあわせて柩(=故人を納めた棺)を火葬場へ移動させ、お別れの時間はほぼ設けられず、予約時間になると火葬されます。よって、直葬はお金はかかりませんが、お別れの時間がない(わずか5分ほど)ことを知ったうえで判断しましょう。「こんなはずじゃなかったのに・・・」というのは、そういうことです。
一部の葬儀社の広告では、その直葬を家族葬プランの1つと誤認させるような表記をしていることがあります。例えば、「家族葬の〇〇社、最安プラン80,000円~」などがそうです。その最安プランが家族葬と言っている訳ではありませんが、誤認する可能性があり、その結果として、2つの問題を引き起こす可能性があります。
1つは、「家族葬が8万円でできると思って依頼したが、お別れの時間がなく後悔する」というものです。通夜式や告別式などの儀式は、故人とのお別れを悔いなく済ませる場であり、家族や関係者は泣き、時には思い出を語らいながら笑う、感情処理の時間でもあります。
そして、もう1つの問題は、「8万円では家族葬ができないと言われ、そのために追加料金が上乗せされる」というものです。通夜式・告別式(葬儀式)をおこなうには、その分だけ料金がかかりますので、当初の想定より高い金額になるということです。
見えない追加料金
次に、葬儀代が思っていたより高くなる要因の2つ目として、「見えない追加料金の存在」について触れたいと思います。なお、冒頭に葬儀代には階層があると書きましたが、それは葬儀のグレードでる基本プランことではく、葬儀代全体の構成要素のことです。
葬儀の料金は、①基本プランの料金、②葬儀に必須にもかかわらず基本プランに含まれていないの料金、③葬儀に必須ではないが追加できるオプションの料金、④人数に応じて変動する事前に確定できない料金、⑤火葬料、で構成されています。さらに、葬儀代ではありませんが、寺院などの宗教家に渡す心づけ(お布施など)が必要です。そして、その「②葬儀に必須にもかかわらず基本プランに含まれていないの料金」が、思っていたより葬儀代が高くなる最たる要因なのです。
それは車に例えると解りやすいでしょう。ハンドルのない車やブレーキペダルのない車が運転できないのと同じように、葬儀をするのに必須にもかかわらず、それが基本プランの料金に含まれていないため、必然的に追加料金が発生することになるのです。
さらに、「②葬儀に必須にもかかわらず基本プランに含まれていないの料金」の例として、もちろん葬儀社にもよりますが、ご遺体の搬送料が含まれていない、司会進行者がいない、棺が別料金、仏衣が含まれていない、後飾り(中陰台)が付いていない、サービス料、遺体保護用品などがそうです。なお、前職で前述の①と②の詳細を葬儀社ごとに比較できるよう一覧にしたところ、驚くほど金額の差が出ました。今や、広告の料金はもちろんですが、②がどれだけあるかを確認のうえ、葬儀社を選ぶことは当然の世の中といえるでしょう。そして、ホームページなどで金額を開示していない葬儀社はお勧めしません。
補足として、「②葬儀に必須にもかかわらず基本プランに含まれていないの料金」がある理由は2つあります。1つは、基本プランの料金を安く見せるため。そして、もう1つは、各葬儀社の会員になると基本プランの価格から10~20%の割引を受けられるのですが、基本プランから外すことによって、割引対象外にすることができるからです。まさに葬儀社にとっては一石二鳥ですね。
ネット葬儀社はどうなの?
ここ数年で、「小さなお葬式」や「イオンのお葬式」「いい葬儀」など、ネット葬儀社が台頭してきました。これらのネット葬儀社は、ネットで集客した顧客を各地域で提携している葬儀社に紹介する「葬儀仲介業者」です。そして、その紹介料は、基本プランの料金に対し20~40%です。依頼を受けた葬儀社がその紹介料を支払うことによって、葬儀仲介業者は成り立っています。
しかし、紹介を受けた葬儀社が40%の紹介料を払うことは決して容易ではありません。なぜなら、単純にその分だけ利益が減ることになるからです。売上高営業利益率が10%を超える企業が少ないといわれている現在、40%の紹介料を払うということは並大抵ではありません。すると葬儀社はそのなかでも利益を出さなければなりませんので、ある2つの方法を選択することがあります。
それは、サービス品質(人件費や備品等のコスト)を落とすか、葬儀仲介業者から依頼があった場合のオプション価格を通常(自社に直接依頼された場合)より引き上げるか。その2つのうちどちらか、あるいはその両方で利益のマイナスをコントロールする方法です。つまり、葬儀仲介業者の紹介料のシワ寄せが顧客の負担に転嫁されている可能性があるということです。その結果、サービス品質と価格のアンバランスが生じることにより、「葬儀代が思っていたより高かった」となる可能性があります。なお、葬儀の料金等に関する国民生活センターへの2024年度の相談が、昨年比で10%増加しています。
まとめ
「小さなお葬式」などネットの葬儀仲介業者に依頼する前に、地元の葬儀社に事前見積もりを取り、希望の予算で葬儀ができるよう相談しましょう。その際、前述の「②葬儀に必須にもかかわらず基本プランに含まれていないの料金」の確認を忘れずに。そのうえで、ネットの葬儀仲介業者に依頼するかどうかを検討しましょう。
もし、葬儀社選びについて相談したいという方がいらっしゃいましたら、今まで葬儀に携わってきた経験と中立的かつ客観的な視点から、私なりにアドバイスさせていただきます。大切な家族の葬儀だからこそ、後悔のないようにしたいものですね。